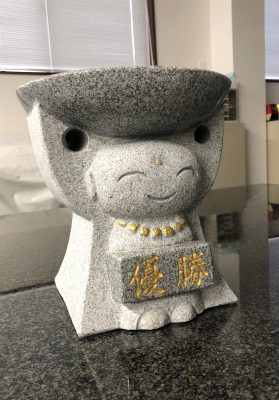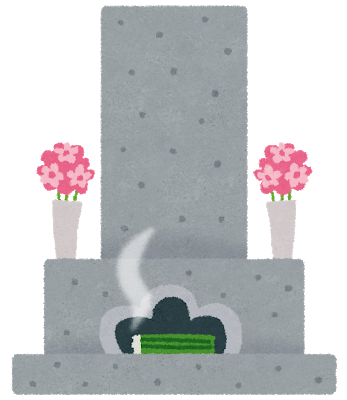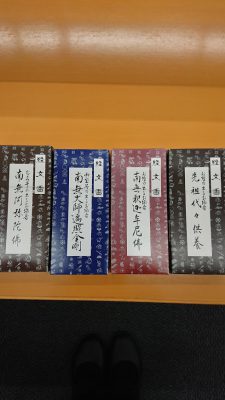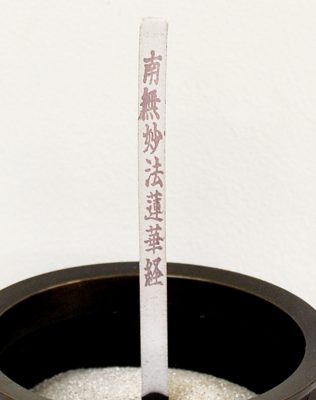仕入れ担当の森田です。
墓石作りは、こんなことから始めるの?
こんなタイトルの動画が日本石材産業協会より公開されました。
動画は3本あります。
【石産協】「ニョキッ!」お墓になる石を山から見つける
https://www.youtube.com/watch?v=oa45CQk03qc&feature=youtu.be
発破のシーンがあって迫力あります。
こんなに粉々になってしまったら、使えるところが無くなってしまうんじゃと思いますが、やはり山は大きいです。
この発破をする前には、当然ながら良い石が(大きくてしっかりした形の)採れることが調べられています。
選ばれた部分がこのように山から外されるわけですね。
【石産協】「うごかない~!」大きな石を割る
https://www.youtube.com/watch?v=2zElsFozFtI&feature=youtu.be
発破で採れた石はそのままでは大きすぎて運ぶことが出来ません。
この大きな石を「割る」という作業が山では行われます。
割りたいところに墨を入れて、それに従ってドリルで穴を開けます。
その穴にセリヤというものをいれて、順番に叩きながら割るという仕組みです。
この方法、古代からずっと変わっていないのです。
古代の石にも一定間隔で穴が空いており、その穴に木製のセリヤを入れて、そこに水を染み込ませ木を膨張させて割っていたのです。
【石産協】「親方~!!」お墓になる石を選ぶ
https://www.youtube.com/watch?v=YESTiajLAmo&feature=youtu.be
大きく割られた石を、更に目的の商品の大きさに近づけるために割るのを「小割り」といいます。
ここからは、実際に注文が入っていればその石塔や霊標のサイズに応じた大きさで取れるように工夫します。
こうしてみると、下台や霊標などの大きな部材はキズを避けると本当に貴重なものなのだなと思ってしまいます。
「お墓の石はエリートです」と言っていますが本当ですね。
今日は山から石が取れる動画をご紹介しました。