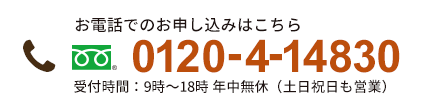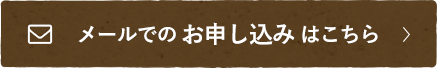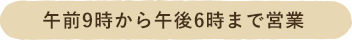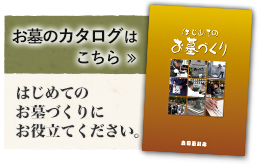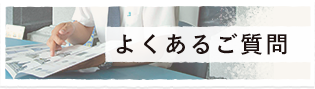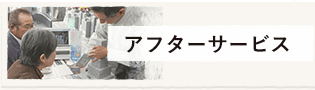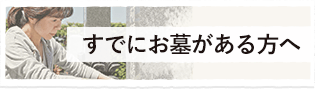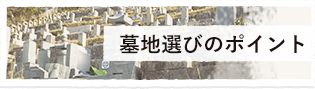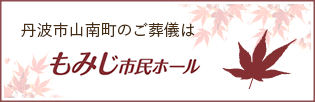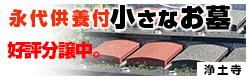森田石材店ブログ - 篠山店 -
英霊碑の移設
2023年07月19日 08:00
今回は、丹波篠山市の村から菩提寺の境内墓地へ英霊碑を移すご依頼を受けました。工事にかかるのは お盆明けになりますが、今日は撥遣供養(はっけんくよう)に参列しましたので、その様子をお知らせします。

この撥遣供養とは、お墓や位牌から魂を抜く法要のことで、お性根抜きや魂抜きと呼ばれています。
村から菩提寺へ移す理由として、英霊の子孫の方々も高齢になってきたことと、同じ村に住んでいない方も出てきて管理が難しくなってきたそうです。
お客様は「村から英霊がなくなるのは少し寂しい気持ちはあるけど、処分するわけではないので菩提寺のもとできっちりと管理されるようになり、逆に良かったかも」と、おっしゃっていました。

次回は、工事の様子を報告します。
【カテゴリ】
墓じまいのお手伝い
2023年06月27日 08:00
今回は、丹波篠山市南矢代墓地でお墓じまいをされたお客様をご紹介致します。
お客様は、今は篠山ではなく遠方にお住まいということで、年々お年を重ねる度に篠山までお参りをしに来るのが大変になってきたそうです。
今後のことを考えてお墓じまいをする決断をしたとのことでした。ただ、村墓地からは離れるけれど、ご先祖様は篠山の地でお祀りをしたいとの希望で篠山の永代供養塔へご納骨することになりました。


お客様からは、ご先祖様のお骨を出来るだけ取り上げて欲しいとのご希望でした。当日は、お客様にも立ち会ってもらい終始工事を見届けていただきました。
しかし、代々墓の納骨堂に入っている焼骨はすぐに取り出せましたが、もう一か所の土葬で埋まっているお骨は、職人に出来るだけ頑張って掘ってもらいましたが出てきませんでした。

お客様がご納得していただくところまで掘り進め、お骨の代わりに一番深いところの土をお客様自身で取ってもらい、骨壺に納めてから供養塔へ納めました。
これで安心出来ると、喜んでいただけました。

【カテゴリ】
丹波茶まつり、行ってきました!
2023年06月21日 08:00
先日のブログでもお伝えしていた「大国寺と丹波茶まつり」へ行ってきました。

行った時間が遅かったので、帰られる方が多かったのですが、それでもちらほらと楽しんでる方がいらっしゃいました。
この数年、お祭りらしい光景をなかなか見ることがなかったので、フラッと立ち寄るだけでも楽しかったです。
お茶畑もきれいな緑でした。

篠山の和菓子屋さんやハンバーガー屋さんが出店されていたり、隣町のリンゴを育てている方が出店されていたり…
みなさん口をそろえて「今日は人が凄かったよ!」と言っておられました。
こうして少しずつ活気が戻り、賑わっていけばいいなぁ~と思いました。
【カテゴリ】
丹波茶まつり、もうすぐです。
2023年06月02日 08:00
こんにちは。
たんば篠山店スタッフです。
もうすっかり梅雨の気配ですね。
丹波篠山市では、6月3日に大国寺と丹波茶まつりが開催されます。
大国寺周辺は茶畑がたくさんあり、この時期は青々としていてとてもきれいです。
茶まつりは行ったことがないのですが、いつも賑わっていると聞きます。
丹波茶壺道中や物産市、アートの展示があったり、なかなか体験できない茶摘み体験、手揉み体験などもあるそうです!
お子様も楽しめそうなビンゴ大会もあるそうです。
10時から開催されますので、ご都合のつく方はぜひ篠山へいらしてくださいね。

【カテゴリ】
旅立つ伊達冠石
2023年05月16日 08:00
こんにちは。
たんば篠山店のスタッフです。
たんば篠山店の展示場には立派な伊達冠石の墓石があります。

森田石材店で働く前は、四角いお墓しか知らなかったので、伊達冠石の墓石を初めて見たときは、びっくりしました。
ご来店されるお客様もよく立ち止まって見ておられます。
「『伊達』ってつくから東北の方の石?」と聞かれる方や (正解です!)
「かっこいいなぁ~」と言ってくださる方も多いです。
そんな伊達冠石が、たんば篠山店から旅立ちました!
展示品を動かすところは初めて見るので、沢山写真に収めました。
まずは竿石。


大事にトラックに載せます。

こちらは竿石をのせている台です。

こちらも置いてあるのと単体で見るのとでは印象が違います!
とても大きいです…!!
もっと写真はあるのですが、今日はこの辺にしておきます^^
篠山店から旅立つのが、天気の良い日でよかったです^^
きっとご先祖様も喜ばれるでしょうね。
愛犬との絆
2023年05月08日 08:00
篠山店事務スタッフです。
7年ともに暮らした愛犬とのお別れで、注文頂いたペット墓です。

とても愛しんで育てておられた、かけがえのない家族が旅立って、ぽっかり空いた穴を埋めるためにも必要なお墓なのかなと思います。
マンションに住む知人は、10年ともに暮らした愛犬が亡くなって2年が経つそうですが、和室の寝室に骨壺を置き朝晩お線香を焚いて般若心経をあげていると言います。
大切な家族を失った悲しみが癒えるには時間が必要ですね。



ペットが安心して眠ることができるように、ご供養の形はいろいろありますが、ご遺骨を身近に置いて手元供養をする事も可能です。
ご自宅の庭に置けるお墓や、お部屋に置けるお墓など。ご自身にとって一番供養しやすい方法を検討されることをお勧めします。
今日も、森田石材店のブログをご覧いただき、ありがとうございました。
【カテゴリ】
音の意味。
2023年04月21日 08:00
こんにちは、たんば篠山店スタッフです。
たんば篠山店には仏壇や仏具が揃っています。木魚、鉦吾、りんも、もちろんあります。
それぞれの音色に特徴がありますよね。
ポクポクポク…ケンケンケン…チーンチーン…
なんでこんなに音を鳴らすのかなと、ふと思ったので調べてみました!
木魚は魚が彫ってありますよね。
魚は昼夜問わず目を閉じない生き物で、修行者に寝ずに精進する事を促している為だといわれてるそうです。

鉦吾は音を鳴らすことで宗教的な雰囲気を高め、仏心を呼び覚まし信仰心を起こす、という思想によるものと考えられているそうです。

こちらの鉦吾は滝野店の物です。たんば篠山店ももうすぐ入荷します^^
りんは仏様にお線香をあげ、手を合わせる際の合図として使われることが一般的です。

調べていると、音を鳴らす仏具には修行僧の居眠り防止の意図もあったと言われていたり、読経の音程やリズムを合わせるといった実用的な意味もあるそうです。
祖母の家はどうだったかな?と思ったのですが、なかなか思い出せず…。孫と曾孫で元気な顔を見せに行かないとな、と思った良いきっかけになりました。
みんなが集える いいお墓。
2023年04月07日 08:00
今回は、五月山霊園で洋墓にご自分のお好きな言葉を彫刻されたお客様をご紹介いたします。
ご依頼のとしては「○○家之墓」と彫刻せずに、いろんな意味でみんなが集える墓に欲しいとのことでした。
そこで今回は「心無罣礙/しんむけいげ」という言葉を彫刻することになりました。これは、般若心経の中に出でくる言葉です。「罣礙」というのは「覆うもの」という意味だそうです。そこから「心を覆っている雲が晴れること」「心に何の妨げもないもの」という意味になるそうです。


今回は、ご自身で書かれた文字をそのまま彫刻をすることもあり、工場まで来ていただき文字見本を実物のお墓に貼って、配置やバランスを調整いたしました。
お客様からは、桜が満開の一番いい季節にみんなが集えるいいお墓が出来たと喜んでいただけました。

京都へ行ってきました。
2023年04月03日 08:00
こんにちは、たんば篠山店スタッフです。
もうすっかり春になり、桜も満開ですね!
先日、たんば篠山店の定休日に息子と京都へ行ってきました!
私は花粉症なので、この時期に外出するの億劫で…。それでも今年こそは!と思い、気合を入れて(ティッシュを持って)行きました!
実はなんとなく、京都まで行きづらそう…と思っていたのですが、丹波篠山市から亀岡まで車で40分。そこからJRで20分ほどの距離で「なんでもっと早く行かなかったんだろう…!」と、ちょっと後悔しました。
京都といえば寺院仏閣だろうと言うことで、まずはここ。

八坂神社です。人が多かったので外から覗くだけにしましたが…。
次は縁結びで有名な下鴨神社です。

ここも桜がきれいでした~^^
小学生になる息子に「鳥居をくぐる時は端を通ること。参拝するときは二礼・二拍・一礼をすること」を教えていたのですが、そのとおりにやってたので成長を感じてうれしくなりました。
その他にも寄り道してたくさん食べたりしたのですが、食べるのに夢中で写真に収めるのを忘れていました…。
ですが、とても充実した休日を過ごせました^^

行きやすいことが分かったので、また近々行く予定です!!!!!
【カテゴリ】
お墓の参りの習慣って・・・
2023年03月24日 08:00
お墓の事について記述された、ある雑誌を手に取って読む機会がありました。
内容はだいぶん端折りますが…
中世の時代(平安時代後期(11世紀後半)から、戦国時代(16世紀)にいたるおよそ500年間)にはお墓参りの習慣はなく、墓地に運ばれた死者はそのまま放置され顧みられることはなく、墓地に名が残されることもなく忘れ去られていきました。
故人の戒名・法名を刻んだ墓標(墓石)が普及し始めたのは、江戸時代に入った頃。今でいう富裕層のみだったようです。
死者に対する周忌供養※も、この頃から定着し始め、幕末に向かうにつれ下層身分の人々にも浸透していったようです。
※亡くなって1年目を「一周忌」、2年目を「三回忌」。その後、七回忌(6年目)、十三回忌(12年目)、十七回忌(16年目)と、3と7の年度に行います。 三十三回忌を「年忌明け」といって弔い上げになるのが一般的です。
墓に名を刻み先祖を供養する習慣をもつことで、自分が死んだとしても子や孫たちが墓参りに来てくれるという安心感と、死の恐怖を和らげることにも繋がっていったのかもしれません。
これから先、時代の移り変わりでお墓の形も変わりつつありますが…。
先日、お墓の相談に来られていたご家族のお話が聞こえてきました。
「いつもお仏壇に『ありがとう』と手をあわせているのだから、墓標にも『ありがとう』と刻みたい」と話されていました。
ご先祖様がいて今の自分があるのだから、感謝の気持ちで手を合わせる。大切な習慣ですね。
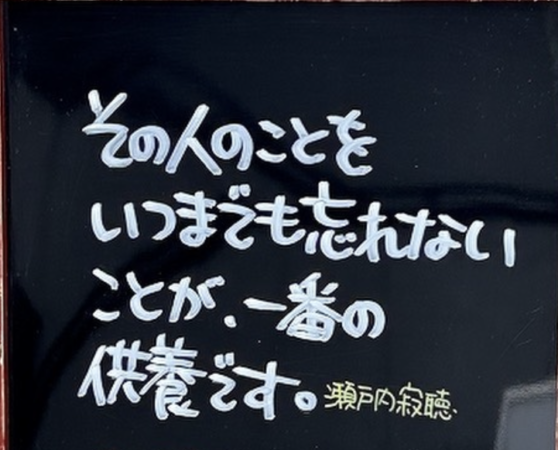
今日も、森田石材店のブログをご覧いただき、ありがとうございました。
【カテゴリ】