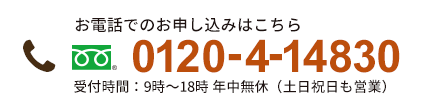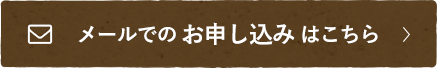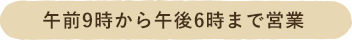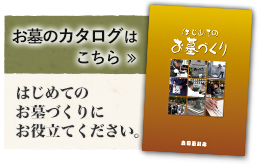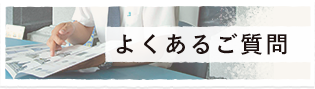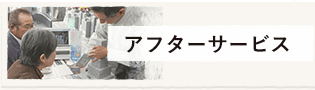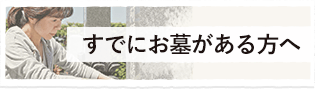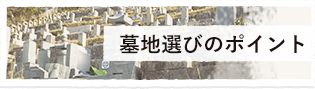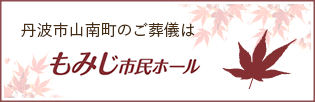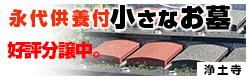森田石材店ブログ - ちょっと考えてみました -
お墓参りの際にやっておきたいこと
2017年12月14日 08:00
【カテゴリ】
鹿に注意!
2017年12月10日 08:00
滝野店の髙梨です。
【カテゴリ】
暦の見方
2017年11月29日 08:00
今年もあと一カ月余りとなりました。
この時期、書店に行くと一番目立つところに「手帳」「暦」がたくさん陳列してあります。
手帳は3年前からGoogleカレンダーをスマートフォンと連動させて使っているので、手帳は使わなくなりましたが、暦は仕事柄使っています。
詳しくはないのですが、先ずは自分の星を診ます。私は昭和40年2月1日生まれ巳年なのですが、暦は立春を境に診るので辰年の「九紫火星」になります。
まずそのページを読んで注意すべきところをチェックし、今年の運勢は良いのか?新しいことを始めても良いのか否か?など判断します。
さて仕事柄、「お墓の工事はいつが良いの?」とお日柄を気にされる方には、暦の六曜(大安・仏滅・友引)のところはあまり見ません。
その下に書いてある「中段・二十八宿・下段」を診ます。
中段であれば(たつ・のぞく・ひらく)などは良い日、反対に(やぶる・あやぶ)などは凶日とあり下段であれば(天恩・神吉・母倉)などは吉日、反対に(滅門・黒日)などは凶日。
二十八宿も(昴・畢・軫)などは吉日、反対に(胃・鬼)などは凶日。できるだけこの三つの吉日が多い日を選ぶのですが、なかなか全て吉日の日は一年の内数日なので難しいです。
しかし、大凶日だけを除けば吉日も結構多いので、お日柄を気にされる方は、一度暦をチェックしてみてください。
見にくいですが、来年の一月をチェックした私の暦です。
ちょっと見ずらいですが、赤ペンの所が凶日です。参考にしてください。
【カテゴリ】
知っておきたい習慣の違い ~神式~
2017年11月10日 08:00
【カテゴリ】
お祭りといえば神社
2017年10月12日 08:00
仕入れ担当の森田です。
【カテゴリ】
お墓に咲く花・・?
2017年10月08日 08:00
本店 山崎です。
【カテゴリ】
墓じまい、悲しい現実です
2017年09月16日 08:00
滝野店 髙梨です。
【カテゴリ】
ファミリーヒストリーとお墓
2017年09月08日 08:00
【カテゴリ】
お墓を契約する時の注意点は何ですか?
2017年08月12日 08:00
【カテゴリ】
三鈷の松
2017年08月04日 08:00
こんにちは、篠山店の上山です。
見つけました。3本の松の葉。通常の松の葉は2本ですが、篠山のお寺の墓地で3本の松の葉を、それも落ちている松の葉のほとんどが3本です。
おそらく、この松の木だと思います。周りの樹木より飛び抜けて大きいです。
有名なのは高野山金剛峰寺の御影堂(みえどう)の前にある松の木で「三鈷(さんこ)の松」と呼ばれています。
今から1200年以上も昔、弘法大師空海が唐(中国)の国へ渡って名州(現在は寧波)の港から帰国の際、師の恵果和尚から贈られた密教法具の一種である「三鈷杵」を東の空に向けて投げました。時に大同元年(806年)であったといいます。
投げた理由は『私が漏らすことなく受け継いだ密教を広めるのにふさわしい地へ行くように・・・」という願いが込められていました。
その後日本に帰ってきた弘法大師が、その三鈷杵を探し求めて各地を歩きまわり、弘仁7年(816年)頃、ついにその光り輝く三鈷杵が高野山の松の木にかかっていることが分かったというのです。
そうしたことによって高野山が真言密教の道場として開かれるようになり、この松を「三鈷の松」と言うようになりました。
三鈷杵の先(鈷部)が中鈷・脇鈷と三つに分かれていることから、その形とあわせて「三鈷の松」とも呼ばれています。

これが「三鈷杵」です、大きさは15cmくらいです。
高野山の三鈷の松の松葉は、お守りとして売られています。「三鈷の松」を財布に入れておくと、幸福になれるとか、お金が貯まるとか言われています。
篠山のお寺の三本の松葉は関係があるのか分かりませんが、良いように考えてみようと思います。
【カテゴリ】