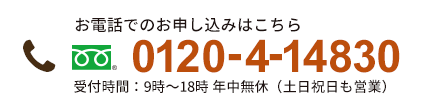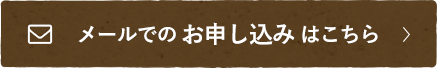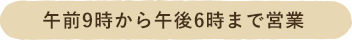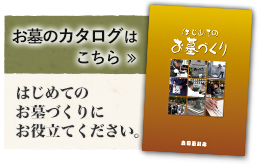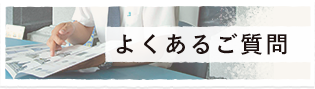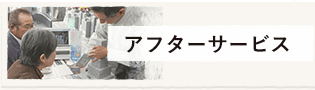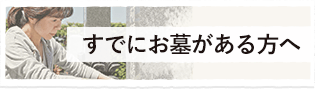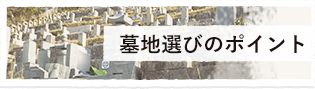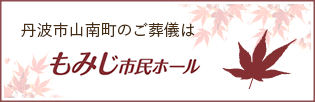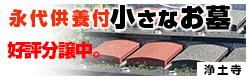森田石材店ブログ - こんな工事もします -
石垣のズレ
2019年02月10日 08:00
こんにちは、篠山店の上山です。
今回、お問い合わせ頂いたのは「墓地の後ろの石垣が崩れたので直してほしい」という事でした。
崩れた石垣は石積みした時期が違うのか積み方が左右で違いました。
石垣の右側は「布積み」
布積みというのは、石と石の継ぎ目が横に一直線に通るように積み上げる方法で目地が通っているので、強度に問題があります。
左側は「谷積み」
谷積みというのは、平石の隅を立てて積む積み方で、石を斜めに落とし込んで積む方法で、力が分散するので布積みより強度があります。
石垣はコンクリートやモルタルを使わない空積み(からづみ)という技法で積まれていて、強度が低いといわれる布積みの部分が膨らんで崩れていました。
崩れていない部分もすべて番号を付けてから解体していきます。
今回の石垣積みは練積み(ねりづみ)という技法で裏込(うらごめ)コンクリートでの施工をしました。
石垣も以前の状態に戻し、これからは安心してお参りして頂けることと思います。
【カテゴリ】
縁起物
2019年01月07日 08:00
こんにちは、篠山店の上山です。
新しい年を迎えるにあたり縁起物の代表でもある『七福神』その中でも特に有名な『恵比寿・大黒天』をご自宅のお庭に納めました。
『恵比寿さま』七福神の中で唯一の日本の神様で、日本神話のイザナミ(女神)とイザナギ(男神)の間に生まれたと言われています。
「恵比寿顔」と言われる癒しの笑顔で関西では「えべっさん」の愛称で親しまれています。
左手には大きな鯛を抱えている通り、海からの恵みを象徴した漁業の神さまですが、今では商売繁盛のご利益があると言われています。
『大黒さま』こちらは、インドのヒンドゥー教の神様、シヴァ神の化身で天台宗を開いた最澄によって日本に伝えられ台所の中心となるカマドを守る神様というようになりました。
右手に「打ち出の小槌」を持って「米俵」に乗っている通り、農業の神さまで五穀豊穣、財宝、福徳開運のご利益があると言われています。
どちらもいい笑顔をしています、今年も皆様が笑顔で過ごされますように。
【カテゴリ】
取り敢えずは…応急処置
2018年12月27日 08:00
滝野店の髙梨です。
先日ユーザー様からお電話いただきました。
「お宮の鳥居にヒビが入ってるんやけど修理できるやろか?」との事でしたので、早速現地へ。
白い目印部分がその亀裂です。柱を一周はしていないものの半周しています。かなり危険です。
この鳥居には「宝暦〇年・・・」と彫ってありました。ですので少なくとも250年程は経っていますが立派な御影石製です。
聞けば昔はもう少し西側にあったものを移設してきたとの事。しかも一度大きな台風で神社の木がこの鳥居に倒れて来て、
中の貫と額が折れて交換したそうです。村の方々は「もしかしたら、その時の衝撃でヒビが入ってたんかな~。
それが何年もかかってこうやって大きくなったんやろ。こんな傷なかったからな」と言われてました。
さて修理ですが・・・正直この段階で修理は出来ず、亀裂箇所と周囲のヒビ割れにセメントを詰める応急処置しかできません。
正直、この処置をしても石の強度としては復活はしません。亀裂から水が入ったり、大きくならないようにする予防策だけです。
トンネル銘板~取付工事~
2018年12月02日 08:00
本店 山崎です。
これまで、「入荷」「彫刻」と書いてきたトンネルの銘板ですが、いよいよ工事の日を迎えました。
今回の現場は、和歌山県です。工事担当の技術部3名は、当日朝4時半頃に会社を出発。現地には、9時頃に到着しました。
その後、さっそくトンネルの銘板の取付です。皆さんご存知の通り、トンネルの銘板は高い所にあります。ですので、高所作業車「スカイマスター」に乗って作業をします。
↑これです!(今回はこの写真を撮り忘れてしまい、これは以前のトンネル工事時の写真です。ごめんなさい。)
このような箱の中での作業になるので、狭くて大変だったそうです。片側に、黒い銘板を2枚貼ります。
一枚取り付けた状況です。工事途中ではないと見れません。
残りの1枚も取り付けて完成です。
この作業を出口側でも行います。この写真は、スカイマスターから撮りました。普段は下から見上げることしかできませんが、このような感じで取り付けてあります。
今回工事をした技術部の担当者に話を聞くと、「めったにない工事なので、この作業をする時は緊張感があった」と話していました。
もちろん!お墓の工事にも気を抜くことなく、見えないところまで念入りに工事していますので、ご安心ください(^^)/
【カテゴリ】
お墓が沈下!
2018年11月05日 08:00
本店の高橋です。
お客様から「お墓がえらい事になっとる。すぐ見に来て欲しい」と電話が。行ってみると、この有り様。

すぐに会社に連絡し工場で作業中の職人を連れて応急処置をさせて頂きました。
右側の花立は隣の石塔にもたれかかっており、墓石上部の細長い竿石も転落一歩手前でした。転落してしまう前に竿石は安全な場所へ移設しました。

傾くというより真下に穴が開いてそこへ落ち込んでいる感じでした。
建立の工事は私どもとは別の業者でしたが、今はすでに廃業されているので弊社に相談されたとの事でした。
全体を点検してみると、他の部分にも沈下が見られたので全体を解体し再度しっかりと据え直す事になりました。
解体してみると地中に大きな空洞があった訳でもありませんでした。全体的に中入れの土がスカスカの状態であり、工事時の転圧不足が原因かと思われました。
囲いの巻石の下のコンクリートベースも所々にしか打設されていませんでした。

もちろんしっかりと転圧し、コンクリート基礎を打って修復し、喜んで頂きました。
【カテゴリ】
トンネルの銘板~②~
2018年10月31日 08:00
本店 山崎です。
さて、先日このブログでトンネルの銘板が入荷した事を書きました。
その後です・・・
文字が本社へ到着し、さっそく実寸に合わせます。手書きですので、機械でカットする事が出来ませんので、手で写して、手でカットです。この時に出来る限り忠実に、綺麗にカットします。
一文字の大きさが、約40㎝程度あります。前回、記載したように2枚で1枚ですので、1枚にトンネルの「ンネル」の3文字が入っています。そして、こののち彫刻に取り掛かりました。
文字彫刻担当者に話を聞くと、通常の石塔「◯◯家之墓」と「建立年月日、建立者」を彫刻するのに、2~3時間かかるのですが、このトンネルの銘板1枚。ですから、この「ンネル」の3文字を彫刻するのに、おおよそ1日かかるそうです。
大きく深く彫刻しないといけないので、かなり大変な作業になります。
彫刻が終わって、白色を入れた分がこちらです。
この後、周りのゴムシートを外して銘板は完成です。あとは、取り付けるだけになります。
【カテゴリ】
一緒にお墓に入ろう
2018年10月09日 08:00
こんにちは、本店の義積です。
10月のこの時期は秋祭りがあちこちで行われいます。
窓を開けて仕事をしていますと、元気な子供の「わっしょい!」という声が聞こえてきます。お神輿を引いているのでしょうね。
突然ですが、あなたがお墓に入るとすれば、誰と入りたいですか?ご結婚されているのであれば、自分のパートナーと思い浮かべますか?
嫁いだら、姑や舅やと共にずっとお墓に入るのは当たり前?更に「墓守りは長男の役目」「お墓の引っ越しはどうする」
そんな話がたくさん出てくる興味深い本に出会いました。
本のタイトルは「一緒にお墓に入ろう」です。
銀行のエリート社員の主人公、旦那のお墓に入るのを拒否した妻、主人公と長年密かに関係を持っていた愛人の三人が奔走するお墓の「墓じまい」がテーマの物語です。
話の内容がとても面白いのですが、ここの物語を書かれた方は丹波市山南町の方なのと、主人公の実家は丹波市の設定なので福知山線が出てきたり、関西弁が出てきたりするのでとても親近感が湧きます。
私は本好きなので読むペースがもともと早いのですが、この本は3時間で一気に読めました。
読書の秋に読んで見られたらいかがですか?(^-^)
【カテゴリ】
トンネルの銘板
2018年09月29日 08:00
本店 山崎です。
先週、工場に大きな黒い銘板が入荷しました。
これは皆さまも何度も目にされた事があると思いますが、トンネルの入口上に取り付けてある黒い銘板です!
「◯◯トンネル」と書いてあるアレです。弊社ではたびたびこのトンネル銘板の工事を請け負っています。
車でトンネルを通る際、ふと見上げるとその大きさはなかなか想像できないかもしれませんが、実際はとても大きいものです。
上の写真の黒い石が2枚1組で、片側の銘板になります。大きいものなので、なかなか1枚で採るのは難しく、このように中心で分割して据えます。
ここに「◯◯トンネル」と彫刻します。その文字の多くは、そのトンネルに関わっている方の自筆(私が今まで見たものだと、地元の小学生、県知事さん、市長さんなど・・・でした)であることがほとんどです。
原稿は通常ですと、半紙に書かれていますので、それを実際の寸法に合わせて調整し、写して彫刻へと取り掛かります。
一文字一文字がとても大きくなりますので、大変です。もちろん、取付工事にも大きな重機が必要となりますので、大がかりな工事になります。
今回のこの銘板の取付は、11月頃を予定しています。まだしばらくは、工場で出番を待つ事になります。また随時お知らせ出来ればと思います(^^♪
【カテゴリ】