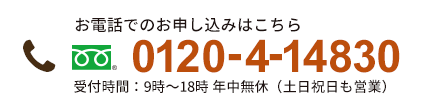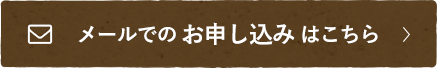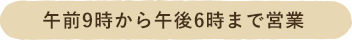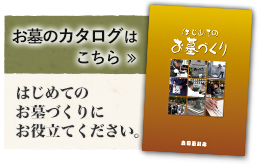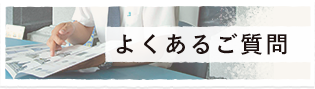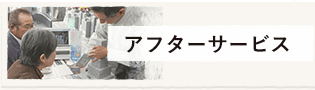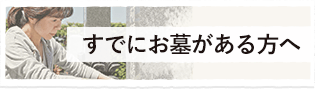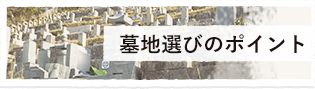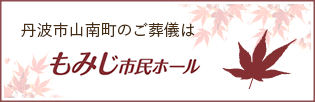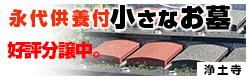森田石材店ブログ - こんな工事もします -
紀州犬の石像
2020年09月15日 08:00
本店の中道です。
紀州犬の石像・2体の依頼がありました。
1体は白い犬、もう1体は黒い犬との事。
以前、真言宗のお寺さんへ同じ様に2体の犬の石像を納めさせて頂いた事があり、その時にお寺様からお話をお聞きしたのが、
『中国の唐から留学をおえて帰国した空海(弘法大師)さんが真言密教の霊場を求めて旅をしていた所、大和の国宇智(現在の奈良県五條市)で、白と黒2頭の紀州犬を連れた狩人に出会い、この犬が空海を保護して高野山の霊場へ導いたと言うお話があるんです』
との事でした。
個人の家でお祀りされている弘法大師さん。
施工前
施工後
白い犬は白みかげ石で研磨はせず毛並みの様にスジを入れた加工にし、黒い犬は黒みかげ石で研磨加工にして石の生地の色を出しました。
ちなみに黒い犬は『九郎』、白い犬は『四郎』だそうです。
真言宗のお寺様に納めた、『九郎』と『四郎』
狛狐(きつね)の据え付け 2
2020年07月17日 08:00
本店の中道です。
伊丹市にある会社の屋上に狛狐を据え付けるお仕事です。
現地を拝見するとなんとかウチの車両のクレーンで搬入することが出来そうなのでひとまず安心しました。
ご注文も頂き、入荷次第すぐに納品してほしいとの事でした。
写真の中央上の手すりの奥にお社があります。
工事の様子です。駐車場からクレーンで吊り上げます。
土台、柱を据え付けます。
中台に狐を据え付けて、最後に台石と台石の間をコーキングで目地をします。
完成です。
石の鳥居もしてほしいと、お話があったのですが、設計の先生に確認したところ、あの場所にあの重量の鳥居設置は構造的にやめたほうがいいと言われまして、やむなく中止となり残念でしたが、
狛狐はとても気に入っていただけました。
【カテゴリ】
銭形水鉢
2020年07月06日 08:00
代表の森田です。
梅雨の侯・・・雨が多いと気持ちも下がり気味ですが、雨降りの庭鑑賞は、ちょっといい感じです。
今まで庭木や石灯籠を鑑賞することはなかったのですが、ゴールデンウィークから草引きを中心に庭の手入れをした事もあり、ほんの少しですが毎朝掃除と水やりをするようになりました。
自分で手入れをすると愛着が湧いてきます。「いつまで続くかな?」と嫌味も言われていますが(笑)
さて、今回ご紹介する「水鉢」は、私が庭石の中で一番好きな石です。石工の業界に弟子入りした時、最初に作らせてもらったのが水鉢で、その時の光景が鮮明に蘇ってきます。
水鉢(蹲居)の中でも「銭形水鉢(銭鉢)」です。京都の龍安寺の銭形水鉢は水戸光圀公から送られたものと言われています。
「吾・唯・足・知」と彫られています。口を中心になんともうまく使ったな・・・唯、感心します。
「吾唯足るを知る」とは、他人と比べてではなく、何が自分にとって必要で何が不要なのかきちんと見極めること・・・昨今「足りる」「満足する」気持ちが麻痺してきている世の中、頭の片隅にいつも持っておきたい言葉ですね。
30年前に据え付けた「銭形水鉢」です。愛知県岡崎市の夏山石で作られたものです。
苔むしって、侘び寂びを感じれるようになりました。
狛狐(きつね)の据え付け 1
2020年06月26日 08:00
本店の中道です。
以前このブログで氷上町の神社で狛狐の工事紹介をしました。
今回そのブログを見て、狛狐を建てたいとの問い合わせのお話をいただきました。
施主様の会社は伊丹市にあると言うことで、据え付ける場所の写真を送ってもらう事にしました。
下がその写真…なんと屋上に据え付けるとの事。
そういえば、都会では屋上にお稲荷さんを祀ってある光景はよく目にします。
細い通路やら、非常階段を上ってお社のある屋上へたどりつきます。
階段を上り終えた所がお社の場所になります。
社長様から一度お会いして、お話も聞きたいとお申し出もありましたので、現地を拝見する事にしました。
【カテゴリ】
松隣寺さま永代供養塔建立
2020年04月17日 08:00
篠山店の園中です。
丹波篠山市の松隣寺さまの境内で、永代供養塔の工事をさせていただきました。
その工事と3月に執り行なわれました開眼式の様子をご紹介します。
まずは工事の様子です。
アスファルトに釘を打ち、水糸を結び付け、アスファルトを切る位置を決めます。ユンボで敷地全体の土を掘り起こします。
ランマーで踏み固めます。納骨堂の下と排水穴を設置し配筋します。
コンクリートを流し込みます。バイブレーターを使い振動を与えコンクリートかな大きな気泡を取り除き、骨材を均等にします。
石垣を積んでいきます。石垣の上に延石を乗せ、組み合わせの所は、ステンレス製の金具を取り付けます。
納骨堂を配置し組み立てます。納骨堂の周囲はファイバーレジンで仕上げ。
宝塔を据え付けて完成です。両サイドに札をつけることができます。
裏側に扉がありこちらからお骨を入れます。内部は両サイドに棚、中央奥に納骨堂を配置。
そして、いよいよ檀家様にお披露目の日。たくさんの檀家さんが参列して下さった中、ご住職の読経が山々に響きわたりました。
境内のどこの場所で建てるか候補地が二転三転しましが、最終的に一番いい所に落ち着き、周囲にマッチしたいい供養塔が出来たと喜んで頂けました。
神池寺の階段の修理
2020年04月08日 08:00
代表の森田です。
この度、市島町の神池寺さまの常行堂の階段修復工事をさせていただきました。
神池寺は丹波の比叡ともいわれています。麓からお寺までは、まるで比叡山と同じくらい登っている感じです。
歴史も古く718年に開創されています。
さて、歴史ある階段の修復となります。修繕工法は、一段ずつ解体をして左右に糸を張り糸の通りに合わせて据え直します。
神社仏閣の修繕工事は多数手がけていますが、多くは凝灰岩で作られているため風化が激しくてボロボロに崩れている物も多いのですが、この階段は安山岩で作られているので、据え直すだけで立派に復元できます。
直した石段の間にコンクリートを入れて完成しました。
この階段を上がった左手に文化財になっている「宝篋印塔」があります。
年代は不明らしいのですが、南北朝時代の作品のようです。
鎌倉時代の石仏は奈良や京都にもたくさんありますが、作りに派手さがなく美しいものが多いです。この宝篋印塔もその一つですね。
機会があればぜひご覧ください。
【カテゴリ】
大歳神社の鳥居
2020年03月19日 08:00
こんにちは、篠山店の上山です。
朝夕はまだまだ寒い丹波篠山ですが、日中は春の兆しを感じられるようになりました。
山の墓地に行くと鶯の鳴き声を聞くようになり、ほっとして聞き入ることあります。
先月に御神木の伐木を終え鳥居の建立を行いました。
基礎ベースの掘削
転圧
配筋
鳥居柱部分を繋ぐようにコンクリート打設することにより、より強度の高い基礎ベースとなります。
数日養生をしての建立になります、台座に取り付けているL字アングルのボルトで柱のコケ(傾き)を調整します。
台座部分を取り巻くようにコンクリート打設、これにより台座部部分の横へのズレを防ぎます。
足元のコンクリートを隠すようにバラスを施し完成です。
数日後の竣工式を待ちます。
竣工式当日は朝早くから氏子の方々に集まって頂き、宮司様のお清めを受けました。
序幕も無事終え記念撮影です。
先代の文字も受け継ぎました。
先代の鳥居が99歳でしたので、新しい鳥居は100年、200年と末永く守り続けられる事を願います。
【カテゴリ】
御神木の伐採
2020年02月25日 08:00
こんにちは、篠山店の上山です。
昨年の11月にアップしておりました鳥居建立工事に伴う御神木の大杉の伐採を、専門業者さんがされるということで安全祈願に立ち会いました。

大型クレーンでの大木の伐採を実際に見るのは初めてです。


業者さんは専門だけあって、段取り良く涼しい顔してクレーンのフックで大木の頂上まで。
高所恐怖症の私ではとてもムリですね。




安全に倒す方向、安全に倒す距離さすがプロ。


樹齢は300年位という事でしたが、木の内部は腐食(茶色の部分)が進んでいてそのままにしておくと倒壊の可能性があったようです。
何はともあれ無事に伐採も終わり、後は弊社の鳥居の建立です。
【カテゴリ】
手水舎の紹介
2020年02月20日 08:00
代表の森田です。
私は仕事柄、神社仏閣に出向くことが多く、その都度写真もたくさん撮っています。写真と言っても「石畳」や「石階段」「手水舎」などもっぱら石ばかりです。
その中でも特に好きなのが「手水舎」です。

こちらは長谷寺の手水舎です。長方形のシンプルな形で手水舎の中では一番多い形だとと思います。水が足元に掛からないように衝立がついています。

こちらは紀三井寺の手水舎です。蓮の形で作られていて、四方どこからでもお清めが出来るようになっています。この写真のものは石造りですが、粉河寺の手水舎は鋳物でつくられていました。

こちらは四国のあるお寺の戦没者慰霊塔に作られていた手水舎です。手水舎というよりは水鉢のようですね。
私の推測では、もともとは水鉢ではなくて、この上に観音様のような仏像が建っていたか?ご寺院様のお墓(さつまいもの様な形)が建っていたか?その蓮華台部分の中を削り取って水鉢にしたのではないかと思いました。
この様な慰霊碑とか小宮さんとかこんな水鉢も似合うと思います。
お正月前にお清めの作法をテレビでやっていましたのでご紹介します。
左手→右手→左手で口を清めて→左手→尺の柄
この様な手順で清めてください。