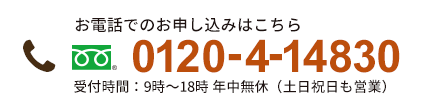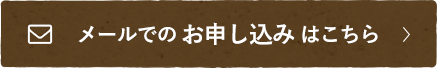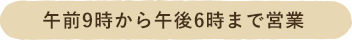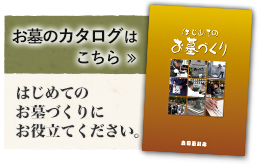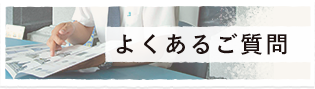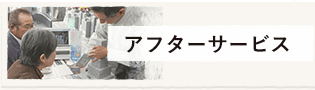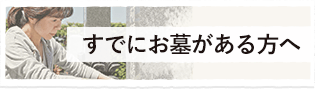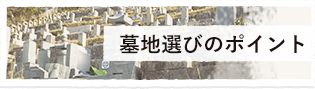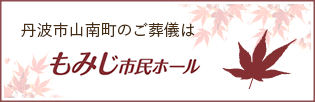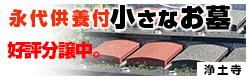本店 山崎です。
本店の癒しのスペースです!
2019年07月26日 08:00
【カテゴリ】
供花を長持ちさせたい
2019年07月25日 08:00
滝野店の福島です。
先日、霊標への追加彫刻を承ったお客様から「せっかくお供えしたお花がすぐに枯れてしまう…」とのご相談をいただきました。
拝見しますと、30数年前に建立なさっているお墓で、花立に穴が空いており、そこに花をお供えされています。
棒の先にハギレを巻き付けて穴の中を掃除なさっているとの事でした。
そこで今回ご提案させて頂いたのが、花立をボーリング(穴を空け直し)、花筒を掃除のしやすいステンレス製の物に交換でした。



暑い日が続きますが、お水もたっぷり入れることが出来、何よりお掃除がしやすくなりました。
お盆も近づいてお墓参りに行かれる機会も多くなる季節です。せっかくのお花です、少しでも長く綺麗な状態でお供え出来ると喜んでいただけました。
【カテゴリ】
全面張石施工のお墓①
2019年07月24日 08:00
滝野店の中村です。
今回はお墓の防草対策のひとつ、張石施工のお話です。
やはりお墓の新設、リフォームどちらの場合もお客様の要望として「草引きをしなくていいお墓」というのは多いです。
今回は打合せの中で「洋風のお墓」「草引きをしなくていいお墓」という強い要望がありましたので「張石施工」をおすすめ致しました。施工前の様子です。亡くなられたご主人が生前中に防草シートを敷いて防草対策されていたそうです。
まずは整地をして転圧していきます。
墓石を建立して張石施工を行います。
完成がこちらです。
「オシャレなお墓が出来たね~」「草引きしなくていいからええわ~」と施主様、ご親戚の方にも大絶賛でした。
【カテゴリ】
なかなか大変でした~花立、線香立交換~
2019年07月23日 08:00
篠山店の真下(ましも)です。
今回は、花立、線香立の交換です。
このお客様とのお付き合いのきっかけは、お社の台をご注文いただき、設置させていただきました。お社設置後に、お墓を拝見しました。
花立と線香立が外すことができなく、お掃除が大変でした。ご説明させていただき、交換のお手伝いをさせていただく事になりました。
現場で、施工班の職人(当社社員)が現場で交換作業を取り掛かりました。

花立を外してみると通常はセメント等で固定されている花立がほとんどですが、今回は鉛のようなもので固定されていました。
通常は現場の工具で交換できたのですが、今回は無理だという事で、当社工場に持ち帰る事になりました。外してみないとわからないものですね。

線香立も同じ固定方法でしたが、こちらは何とか現場で交換できました。


施工班の職人には手間をかけてしまいましたが、お客様は喜んでいただけたと思います。
他社さんで建てられたお墓のリフォーム工事は多く手掛けさせていただいています。今回のように、仕事を始めてみないとわからない事も多くある、リフォームあるあるなのです。
こんな事もありますが、喜んでいただけるよう、お手伝いを続けていきたいです。
インドの奇跡「天竺~てんじく~」
2019年07月22日 08:00
仕入れ担当の森田です。
今回は、たんば篠山店に展示しております「天竺(てんじく)」をご紹介します。
この「天竺(てんじく)」ですが、その意味はというと日本・朝鮮・中国で、インドの古称。
つまりインドそのもののことを指します(今のインドと正確には一致しないようです)。
こちらは中に建っている墓石が天竺です。自然の石の肌を使って加工されているのが特徴です。
外柵はG623で、前面の拝場には鉄平石が貼られています。印と和の調和といったところでしょうか。さて次はこちら、

先ほどのものよりも、もっとインドでないと作ることができないセットです。
中に建っている墓石のみならず、墓誌(霊標)も、そして更に外柵までもが自然石の肌を生かした作りになっています。
この石はM1Hと呼ばれる石ですが、稀に玉石でこのような「皮」が使える状態になっているようです。玉石ですので切ってみないと中のことは分かりません。キズがあれば使い物になりません。
そんな訳で、インドでないと作ることができない石なのです。
当社では現品を展示しております。お気に召された方はそのままお持ち帰りお買い求めください。
もしオーダーメードで自分の気に入った大きさや形にしたい方はお申し付けください。
但し、その場合には6ヶ月ほどお待ちいただくことがあります。
【カテゴリ】
心静かに・・・
2019年07月21日 08:00
【カテゴリ】
レッカーを使って墓石建立
2019年07月20日 08:00
【カテゴリ】
地盤工事をしっかりと③
2019年07月19日 08:00
滝野店の髙梨です。
この工事も今回が大詰めとなりました。
これまで地盤調査、地盤対策「D-BOX」、ベタ基礎コンクリート工事と説明してきましたが今日の報告は本来の墓石工事となります。
基礎部分をしっかりとしましたが、こちらの墓地は通常の納骨部(カロート)とは違い、

延材を使用し、外柵部分とがっちりと金具で固定し、この上ない強度となりました。

表面の仕上げはもちろん「ファイバーレジン」で仕上げました。こちらの墓地のように鬱蒼として、周囲を木々で覆われた墓地には最適です。

土葬が点々と点在していた墓地とは全く違い、お参り、お手入れしやすく、先の先まで墓守の出来る「しっかりとしたお墓」が完成致しました。
【カテゴリ】
自然石のお墓
2019年07月18日 08:00
篠山店の園中です。
今回は、石本来の風合いを生かした自然石のお墓のご紹介です。
既存石塔の並びに、寿陵墓を建立します。
それでも、展示場で実物を見てお話をとご来店いただいたところ、この墓石に一目見た瞬間に心を打たれてしまい自然石のお墓に!と思い立ったそうです。

正面の彫刻をする面だけは、研磨をしてツヤを出しますが、それ以外の部分は削らずに自然の風合いの皮肌そのままの形でお墓にします。
また、加工していないそのままの皮肌は、年々風合いや色合いも変わっていきます。それも研磨した墓石と違った自然石の魅力の一つです。
多くの場合玉石の中は、傷やムラがたくさんあります。傷やムラが少ないものは、本当に数少なく希少な石なのです。
工事は、墓石を建てるだけではありますが、既存の巻き石を使用するので、補強の為、延べ石と延べ石の組合せの所に、ステンレスの金具を取り付けます。
既存碑の横に建ちました。しかし、これで終わりではありません。

これからの季節、気になるのは「雑草」です。お手入れを楽にするために、玉砂利仕上げではなく「ファイバーレジン」仕上げにします。

これで完成。とても味のあるお墓に仕上がりました。他には無い自分らしいお墓が出来たと喜んでいただきました。
【カテゴリ】
祭壇掛け2
2019年07月17日 09:00
滝野店の吉田です。
今回は、祭壇掛けの採寸の注意点を幾つか書いてみます。まず、祭壇掛けをどの位置まで敷くのかによって、仕立て巾が決まってまいります。
扉が無い場合、若しくは閉めない場合は、ひな壇したの地袋まで祭壇掛けを延長しても問題はないですが、扉を閉める場合には、注意して採寸をしまければなりません。

矢印の戸当たりまで祭壇掛けを敷く場合は、扉の取り付け分の寸法をひな壇の間口寸法より引かなくてはいけません。

上の写真のところの寸法を左右分、ひな壇の間口寸法より合わせて引いて下さい。
取り付け柱のところまでで祭壇掛けを納めるならば、ひな壇の間口寸法にてOKです。今回は、戸当たりまで敷くことにしましたので、取り付け柱の寸法を引いて段取りさせていただきました。
今月中には製作出来ますので、新しい祭壇掛けにてお盆を迎えていただけます。
【カテゴリ】