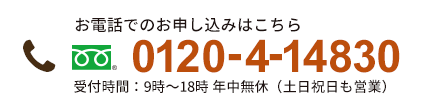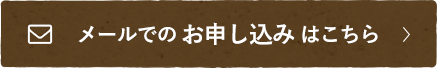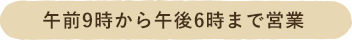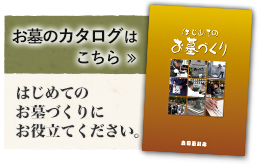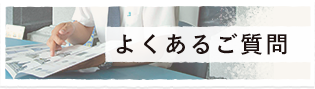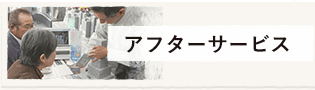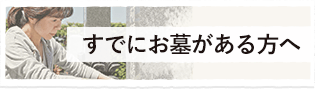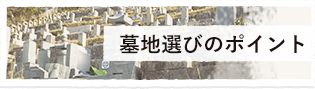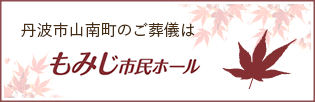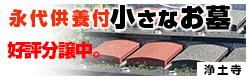本店の髙梨です。
先日、ご納骨のお手伝いをさせていただきましたお客様…実は約半年前にはお墓撤去を考えておられ、その御見積もさせていただいてました。
ある時「主人が亡くなりました。お墓を無くす話していましたが、お骨を納める場所もすぐにはなく、家族で相談して(遠方ですが)出来る限り、お墓参りをしよう決めました。」というご連絡をいただきました。
お墓を建てさせていただく者からすれば、撤去は悲しい話です。
ですので、お悔やみごとが原因ではありますが撤去が回避されたことは少し救われた気持ちにはなりました。
納骨当日は立っているのもやっとなくらいの快晴で真夏日。汗は止まりません。
そこで「残したい出来事なので写真撮ってください。」と頼まれ、カメラを渡されました。最後にお墓や遺影も入れて皆さんで記念撮影もしました。
後日、一通のお手紙が同封されたメール便が髙梨宛で届きました。
「是非とも髙梨さんには見ていただきたく、勝手に送らせていただきました」と。
そこには当日、僕が写した写真を纏めた一枚のアルバムとお元気な姿と闘病中のご主人様や子供さん、お孫さんの家族写真を纏めたもう一枚。
それにお墓があったからこそ、感じていただいた喜びと感謝のお言葉が綴られていました。
何気ない毎日の、慣れた仕事を繰り返していますが、この一通のお手紙と写真の数々は、仕事に対する姿勢や大切さ、影響力を教えて頂けた、とても大切なものになりました。












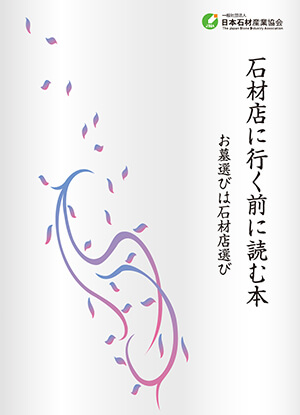









-400x398.jpg)
-400x380.jpg)