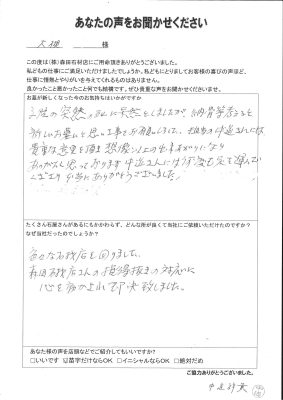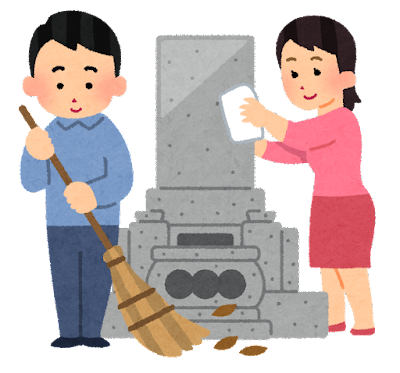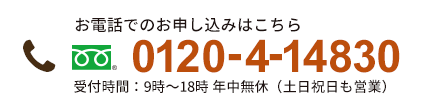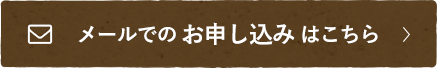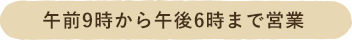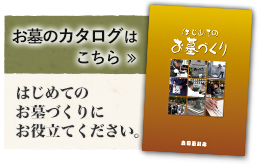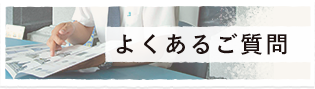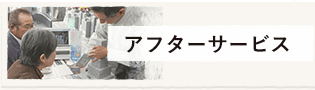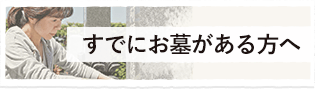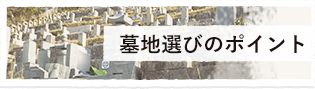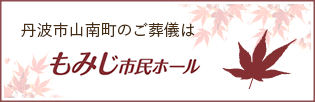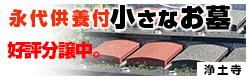代表の森田です。
弊社は創業103年を迎えました。
今年1月に100年を節目とした記念誌が出来上がりました。
内容は初代藤四郎(祖父)が手掛けた神社の鳥居や狛犬、記念碑など現在に至るまでをまとめました。
調べていくと、当時の道具でこれだけの作品を作るのは大変な技術と労力が使われたと思うものが多く、改めて感動した次第です。
ご興味のある方はお問合せください。

さて、開いているページの「信太森神社(葛葉稲荷神社)」のご紹介をさせていただきます。

一番最初にご縁をいただいたのが、2007年(平成19年)です。
本殿の屋根(檜皮葺)を友井社寺様が手掛けておられ、屋根の吹き替えに合わせて修繕をすると言うことで、基礎工事を請けたのがきっかけです。
初めて神社を見たときは、本殿を始めあらゆる構造物が傾いていました。
「わぁ~これは大変だ~」と思いました。


基礎石は隙間が空いて、いろんな方向に陥没していました。
工事手順の最初は。本殿前の「灯篭・狛狐」などを解体・移設し、本殿を仮移動する場所をつくります。
次に本殿をジャッキアップして、家引きさんと呼ばれる方が約20メールほど移動されました。
原始的ではありますが、ジャッキーアップした下にコロ(丸い棒)を敷き動かします。
改めて、この様な工法で建物が移動できるのは日本建築の凄さ、木造建築の良さだと思いました。
建物は移動した後は、土台石の解体工事です。

土台はみかげ石(花崗岩)が使われ、繊細な仕事がされていました。
手加工で隅々までキッチリと合わされている仕事を見ると、当時の石工さんの腕の良さがわかりますし、
「よっしゃ、俺がきれいに復元してやる」とワクワクしてきます。
まず、解体前に同じ場所に同じ石がくるように番号を墨付けをし、痛めないように解体をしていきます。
解体が完了後、基礎工事に掛かります。

本殿場所、全体を約50センチの深さで掘削します。

全体を鉄筋で敷き詰めて、コンクリートを流し込みます。

完成した基礎ベースの上に、解体をした土台石を据えていきます。
当然、上手く合うところと合わないところが出てきます。
手加工で作ってあるものを機械を使って修正すると違和感が出るので、手加工道具を使って当時のままを復元していきます。
普段は使うことのない「1級技能士の技」がこのような時に発揮されます。
土台石を組み上げたあとは、補強のコンクリートを裏側に入れて、基礎工事完成となります。

仮移動していた本殿を新しく出来た基礎舞台に戻します。
この後は、宮大工さんが傷んだ箇所を修繕され、同時に屋根の吹き替えとなります。
屋根は、檜皮葺から銅板葺きに変更されました。
今回の基礎工事をスタートに第2弾、第3弾と続きます。